トップメッセージ
ノリタケ創立以来、最大の変革期。
飛躍に向けて挑戦する私たちに、ぜひ大きな期待を。
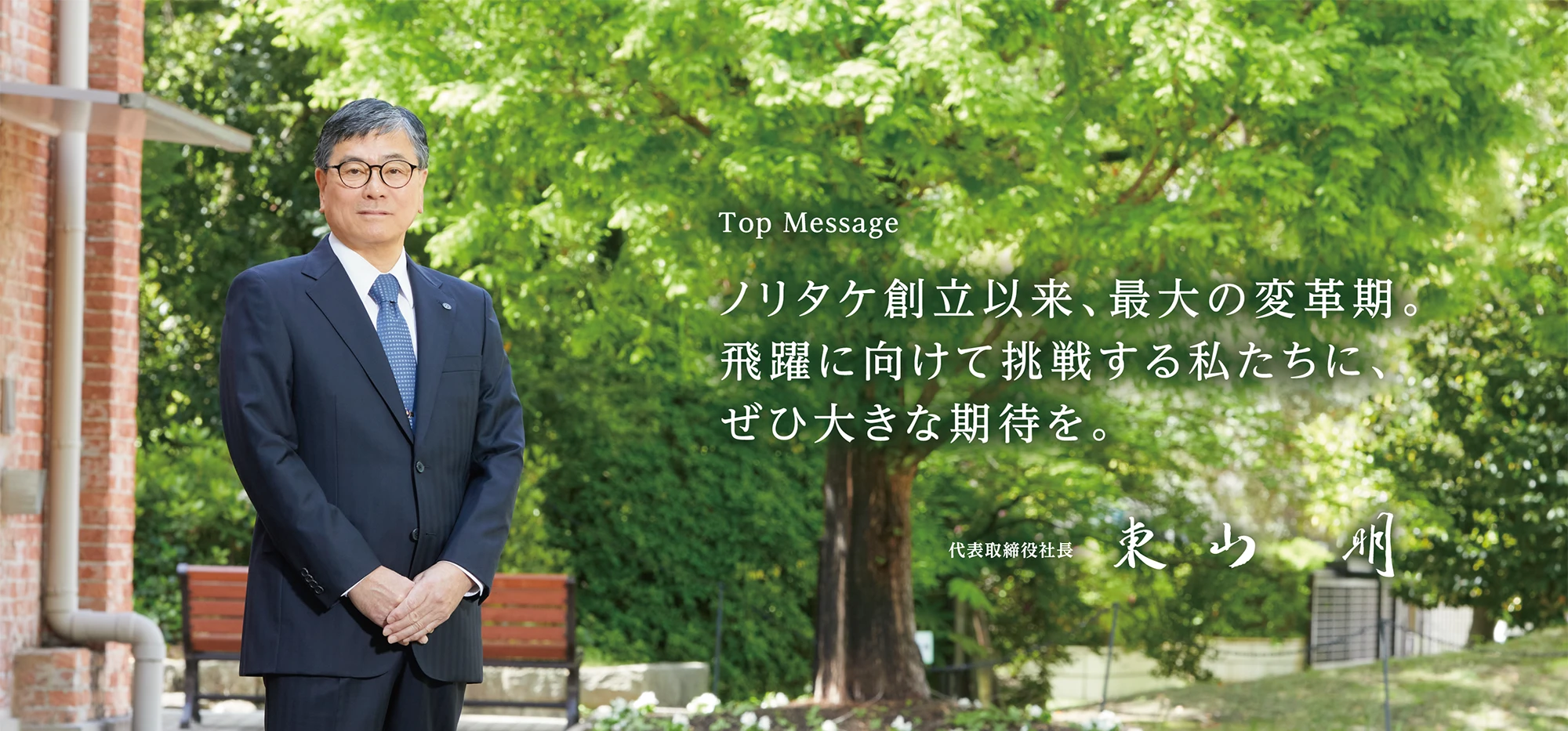
就任初年度となる2024年度の業績と振り返り
第12次中期経営計画(以下、第12次計画)の最終年度である2024年度は、国内では、個人消費は一部に足踏みが残るものの持ち直しの動きがみられ、企業収益が総じて改善する中で設備投資も堅調を維持するなど、景気は緩やかに回復しました。海外では、米国は個人消費を中心に景気が拡大し、欧州は持ち直しの動きがみられましたが、中国は不動産不況を背景に足踏み状態が続きました。引き続き、国内は緩やかな回復が期待されますが、物価上昇の継続による影響が懸念されるほか、米国の保護主義的な通商政策が世界経済に与える影響は計り知れず、先行きは不安視されています。
こうした情勢のもと、ノリタケグループの業績は、売上高1,382億円(前期比0.2%増加)、営業利益102億円(前期比4.6%減少)という結果でした。成長領域のエレクトロニクス分野向けである積層セラミックコンデンサ(MLCC)用電子材料やリチウムイオン電池(LiB)用焼成炉が堅調で、為替の影響もあり増収となりましたが、原材料などの諸物価の高騰を受け、営業利益は減益となりました。
当社グループは以前から、収益性の向上が課題でしたが、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で業績が落ち込んだことでさらなる危機感を抱き、構造改革をスタートさせました。経済環境がめまぐるしく変わる中でも業績を維持・向上する力をつけるために、低収益体質からの脱却を目指し、さまざまな取り組みを進めました。その結果、当社グループの収益力は向上し、営業利益は安定して100億円規模を計上できるようになりました。
社長に就任してからは、「さらなる成長に向けた変革」を目指し、今後も成長を続けていくため「会社のイノベーション」「新事業創出の種づくり」「組織風土改革」の3つのキーワードを掲げ、スピードと変化への対応力の強化に着手しました。
まず「会社のイノベーション」では、従業員エンゲージメント向上のための働きやすい環境づくりや生産性の向上、新事業創出の土台づくりなどを目的として、施設や設備の更新、制度の変更、事業所の再編などに取り組みました。今後も現在のノリタケに必要なことを見極め、必要なものは残し、不要なものは見直すといった取り組みを着実に進めていきます。

「新事業創出の種づくり」では、事業の開発段階から事業化まで、グループ全体の知見を結集させる組織横断の体制づくりと、外部との連携など自前主義からの脱却の2つの軸で取り組みました。全従業員から開発テーマを募り、事業化を早めるステージゲート制度の導入を行い、また、新事業創出のスピードを加速するため、オープンイノベーションの推進体制を整備し、スタートアップやパートナー企業など他社や公的機関、大学などとの連携を強化しています。これらの取り組みは着実に成果を上げており、いくつかの新製品の種を生み出すことができました。
「組織風土改革」は、変化に対応し、会社としてレベルアップするための組織風土づくりとして、新人事制度の導入やタウンホールミーティングを行いました。この一年間、国内の事業所、工場を回り、1,200名を超える従業員と直接対話しました。従業員の生の声を聞くことで現場の状況や従業員が抱える不安や会社への希望などを把握することができたと同時に、会社の方向性や私の考えを伝えることもでき、従業員と想いを共有する良い機会となりました。
第12次中期経営計画の戦略と成果
戦略と主な施策
第12次計画は、2030年度のありたい姿の実現に向けて、「収益基盤の強化と成長領域への仕込み」の期間と位置付けました。『収益基盤の強化』として、不採算商品・事業の再編、収益改善・合理化を行い、『成長領域への仕込み』として増産·拡販への対応を行い、『経営基盤の強化』の取り組みも開始しました。そして、これらを進めるための基盤づくりとして「新事業の創出」「組織風土の改革」「サステナビリティ経営体制の整備」「DXの推進」の4つの全社横断テーマに取り組んできました。
数値目標に対しては、市場環境が当社の想定を下回り、売上・利益ともに未達に終わりましたが、2030年度のありたい姿の実現に向けて、土台作りはできたと認識しています。
『収益基盤の強化』としては、日本レヂボン株式会社と株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ(NCA)の統合、サイアムコーテッドアブレーシブ(Siam Coated Abrasive Co., Ltd.)の完全子会社化などによる事業再編、顧客とのコミュニケーションを通じて当社製品の市場での立ち位置を確認し、価格の適正化や不採算商品の整理に繋げたほか、原材料の見直し、工場の整流化などによる原価低減などを実施し、一定の成果が得られました。
『成長領域への仕込み』については、需要の拡大に合わせて、MLCC用電子材料の生産能力増強を進めたほか、小牧事業所にLiB用焼成炉の増産体制を整備しました。

『経営基盤の強化』としては、以下の4つのテーマに取り組みました。
新事業の創出
全社横断タスクフォースから新事業創出委員会への移行と、開発テーマ提案制度とステージゲート制度の運用を開始し、事業化プロセスの構築に取り組みました。新事業創出はノリタケグループにとって非常に重要性が高い取り組みのため、私が研究開発センター、知財企画部担当役員を兼任し、新事業創出委員会の活動と研究開発センターの活動を連動させるなどの取り組みも進めました。また、特許の管理を担当する知財企画部のメンバーと事業部の連携を強化し、知的財産の取得・活用のサポートをする体制を作り、活動を推進しました。これらの取り組みは、次の中期経営計画で必ず成果に繋がるものと思っています。
組織風土の改革
2024年4月に「チャレンジ」をキーワードとした新人事制度を導入し、評価基準を刷新しました。合わせて、エンゲージメントサーベイを導入し、その結果から明確になった部門ごとの課題の改善を進めました。これらの施策を推し進め、従業員が個性を発揮し生き生きと働ける組織風土を作ることで、従業員のポテンシャルを引き出し、最大限に活かすことができたなら、当社は間違いなく大きく成長できると確信しています。
サステナビリティ経営体制の整備
2023年4月にサステナビリティ統括委員会を発足させ、2024年度には、同委員会のもとにリスクマネジメント委員会を加え、さらなる体制の強化を図っています。マテリアリティについても特定し、中長期的な目標設定を行いました。毎月の経営会議や取締役会でこれらマテリアリティを一つひとつ議論し、進捗についても報告しながら取り組みを進めています。
DXの推進
全社横断タスクフォースを立ち上げ、DX推進リーダー育成プログラムを実施し、一期生として33名のDX推進人材を育成しました。2024年10月にはタスクフォースから「DX推進委員会」へと移行するとともに、DX推進リーダー育成プログラムの第2期を開始、各事業部に所属するDX推進人材が連携し、全社的にDXを推進する体制を構築しました。また、これまで培ってきた技術の活用を目指してMI※を導入し、新材料開発の成功事例が生まれましたので、DX推進委員会でも開発プロセスを共有しました。
※ MI(マテリアルズ・インフォマティクス):AIをはじめとする情報科学の技術を活用し、材料開発を迅速化する手法
各事業についての総評
ノリタケグループは、今後も成長し、社会に貢献できる企業であり続けるために、新しい顧客、新しい市場の開拓を目指し、環境・エレクトロニクス・ウェルビーイングの3分野を成長領域と定め、それぞれの事業で取り組みを推進しています。
工業機材事業は売上高構成比約40%を占める当社の主力事業です。第12次計画の初年度である2022年には、生産拠点の再編やシステムを共通化することで効率化を図るべく、グループ会社である日本レヂボンとNCAを統合し、汎用品事業の再編を行いました。また、工業機材事業はこれまで主に、お客様それぞれのニーズに合わせた製品を提供してきましたが、それだけでなく、成長領域における市場ニーズと事業の将来を踏まえた新しい商品の開発に注力しました。特に、半導体などのエレクトロニクス分野は今後の成長が大きく期待できる分野と考えており、当社の技術の強みを活かした研磨工具などの新製品を展開すべく、開発に取り組んでいます。さらに、既存の、製品別に構成された組織ではなかなか新たな発想や枠組みを超えたアイデアの創出は難しいと考え、2025年度からは、市場別の組織に改編し、新体制で成長領域への事業転換を加速しています。
セラミック・マテリアル事業は、お客様の要望に合わせてさまざまな材料を提供してきましたが、MLCC用電子材料以外は一つひとつの市場が比較的小さな商材が多く、価格の適正化の遅れもあり、収益力に課題がありました。第12次計画では、事業の再構築に取り組み、収益改善に向けては、不採算商品からの撤退と価格の適正化などに取り組んだほか、成長領域向けの新商品開発が不可欠として、エレクトロニクス分野の中でも特にパワー半導体周辺材料への参入を目指すために、2025年度には営業部を一本化し、組織の機能強化を行います。さらに基盤強化として、蛍光表示管の製造・販売を行い、印刷技術に強みをもつノリタケ伊勢株式会社に、厚膜回路基板と転写紙に係る事業を一本化し、収益性の向上や事業体制の効率化に取り組んでいます。

エンジニアリング事業は、近年、LiB用焼成炉を主力に事業を伸ばしてきました。第12次計画では、LiB用焼成炉の増産に向けた投資を進め、小牧事業所にLiB用焼成炉の組立工場を建設したほか、流体事業でもテストセンターを新設しました。2023年には、超硬丸鋸切断機に係る事業を株式会社ノリタケマシンテクノに統合し、インフラ市場での迅速かつ効率的な事業拡大を図っています。ほかにも、蓄積した幅広い技術を活かして、バイオ医薬や半導体といった新しい市場向けの新装置開発に取り組んでいます。装置の開発、販売だけでなく、メンテナンスや消耗品などアフターサービス事業を拡充し、新しいビジネスモデルの確立、収益安定化も図っていく考えです。また、エンジニアリング事業でも2025年度から新事業推進部を新設し、成長領域での事業拡大を目指します。
食器事業は当社の祖業ですが、赤字脱却が最重要課題となっていました。赤字が続いた大きな要因は顧客ニーズの変化に合わせた事業変革ができていなかったことだと認識しています。第12次計画では、共働きのご家庭やひとり世帯でも便利にお使いいただけるよう、食洗器・電子レンジに対応した商品の拡充やオンラインショップの充実に注力したほか、業務用についても、現在注力しているホテル、レストランといった外食産業のニーズの変化に対応したシリーズを拡充するなどの改革を行いました。加えて、さまざまな収支改善策を積み重ねた結果、2024年度は黒字化を達成することができました。
いずれの事業も市場で長く受け入れられていましたが、変化がめまぐるしい今、事業領域の転換が急務だと認識しており、2030年度に向けてさらに成長していくために、今後も「変化への対応力」を強化していきます。
第13次中期経営計画(2025~2027年度)の概要
2025年度からスタートした第13次中期経営計画(以下、第13次計画)は、VISION2030「マテリアル×プロセスの独自技術で変化する社会の欠かせない推進役へ」の実現に向け、「成長基盤の確立」の期間と位置付けます。
第13次計画では、両利きの経営として、「強固な収益基盤の構築」と「成長加速に向けた投資」を推進するとともに、これらを推し進めるため、「経営基盤の高度化」に取り組みます。
強固な収益基盤の構築
成長領域への事業転換を図るため、第12次計画で実行した投資も活用しながら、第13次計画でも積極的な投資を行い、増産・拡販を進めるとともに、新商品開発に取り組みます。また、物価上昇が続いていることもあり、さらなる原価低減、合理化を進め、価格の適正化、老朽化設備の更新による効率化なども推進し、収益の改善を図ります。既存事業においては外部連携も活用し、参入できていない前後工程へ製品投入の範囲を広げたり、既存商品の新用途開拓で対応領域を広げたりすることで、高付加価値・高収益な事業機会を獲得し、強固な収益基盤の構築に取り組み、収益力を強化します。
成長加速に向けた投資
従来の事業ごとの製品起点ではなく、市場起点で成長領域における事業横断での投資機会を探索し、M&Aや資本提携などの企業連携を進めます。また、第12次計画でスタートした開発テーマ提案制度とステージゲート制度を継続し、全社一丸となって新事業を生み出すことを目指すと同時に、自前主義にこだわらず、オープンイノベーション、スタートアップ企業などをはじめとする他社との協業やオープンイノベーション支援拠点「STATION Ai」の活用といった、戦略的な社内外連携を通じて早期の新事業創出を加速させます。
事業成長を後押しする経営基盤の高度化
持続可能な社会の実現に向けた社会課題の解決を目指し、サステナビリティ経営の推進、人的資本経営の強化と、DXの推進に注力し事業成長を後押しし、VISION2030の実現を目指します。
企業には今や財務面だけに留まらず、ESG、経営戦略、知的財産、人的資本、従業員エンゲージメントの領域でも多くの要件を満たすことが求められています。
サステナビリティ経営の推進に取り組むなかでは、製造プロセスで排出する温室効果ガスの削減や省エネ・環境配慮製品を増やす取り組みや、生物多様性の保全に関しても事業所敷地内の緑化をはじめ、環境保護に向けてさまざまな取り組みを進めています。加えて、知的財産(特許、商標、意匠、著作権など)の適切な管理・活用、個人情報を含めた情報資産の保護などのセキュリティ強化、取締役会の実効性の維持・向上といったガバナンスの強化にも引き続き努めます。
人的資本経営の強化としては、事業戦略の遂行に求められる人材像を再定義し、目指す人材ポートフォリオを設定しましたので、それらの人材の能力発掘と評価の両方の仕組みづくりを推進し、当社の人的資本の価値を最大限に引き出していきます。多様な人材を確保し育むことを目的としたタレントマネジメントシステムの活用を進めているほか、先述のとおり、新人事制度の導入を行いました。タウンホールミーティングなどを通じて、改めて全社を見渡してみると、当社にはユニークな才能を持つ人が多くいることがわかりました。これまでの人事制度では、その人たちを評価する基準がなく、そもそも評価されにくかったのですが、新しい人事制度では、コースや等級の定義、評価基準を見直し、実績はもちろん挑戦する姿勢も評価される仕組みとしました。今後、この新人事制度の定着を図り、従業員のチャレンジ精神の醸成とエンゲージメントの向上に繋げ、組織風土改革を実現します。
DXについては、市場や競争環境の変化にスピード感を持って対応できるよう、社内データのデジタル化によって効率化・高度化の基盤を構築し、MI・AIの活用による開発の促進や、業務フローの最適化、製販技連携の活性化などの取り組みとあわせて、中核となるDX推進人材を育成し、内部プロセスの抜本的な変革を目指します。
この第13次計画は、成長のための種をまき、芽を出し育てる期間と考えています。今後の成長を加速するため、投資は350億円から500億円と、これまでのノリタケとしては最大規模を計画しています。ノリタケグループは、今、変わらねばなりません。当社の歴史の中で、まさに最大の変革期です。ノリタケグループが今後も必要とされ、社会に貢献していく企業であり続けるために、確実に計画を実行していくという強い覚悟をもって、この第13次中期経営計画に取り組んでまいります。
ステークホルダーの皆さまへ
ノリタケグループは、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営方針と位置付け、第13次計画では、株主さまへの還元も拡充します。従来30%としていた配当性向を35%に引き上げ、第13次計画期間においては、1株当たり年間140円を下限とした累進配当を実施し、機動的な自己株式取得を行いながら、3カ年累計の総還元性向を50%以上とさせていただきます。
近年、東証による日本の上場企業のPBR(株価純資産倍率)水準の低さに関する指摘が取りざたされています。PBRは自己資本に対する利益率の指標であるROEが上昇することで上がっていきます。利益を上げるには、将来の利益を生むための投資を増やすことで、利益の拡大が見込める領域への事業転換を図り、成長事業を伸ばすことが必要です。当社グループでは、早期のPBR1倍の実現やROE9%以上を第13次計画の目標と設定しましたので、その達成を目指し、経営戦略を実行していきます。
そして、先にも述べたように、10年先、20年先の当社グループが、今後も社会に必要とされ、貢献できる会社であり続けるために、私たちはこれからの3年間で成長基盤の確立を実行していきます。第12次計画で行ってきた収益力の向上に加えて、成長加速に向けた投資を推し進めるために外部との協業をはじめ、新たな取り組みを進めます。
新しいことに取り組む時、誰しもプレッシャーを感じてしまいますが、私は、この挑戦を従業員一人ひとりが自分の夢や希望を叶えるための挑戦だと思ってほしいのです。夢を叶えると思えば、心配よりも喜びの方が大きくなるはずです。リスクばかりを考えるのではなく、チャレンジすることへのワクワクする気持ちを持って前向きに取り組んでもらえるように、私も全力で後押ししていきたいと考えています。たとえ失敗したとしても、それを糧に成功するまでやり続ける、私は当社グループをそんな強い会社にしていきます。ステークホルダーの皆さまには、果敢に挑戦する私たちをぜひ応援してくださいますようお願い申し上げます。









